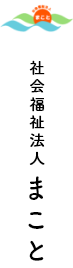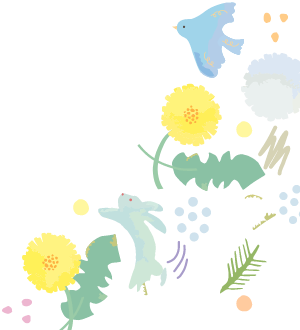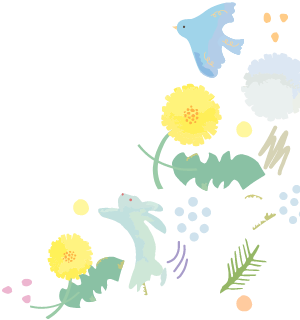皆さんは『春の七草』(ゴギョウ、ホコベラ、スズナ、スズシロ、セリ、ホトケノザ、ナズナ)についての方が、お正月でごちそうを食べた内臓をいたわる食事として馴染み深く、現代の風習でも残っていますね。1月7日(人日【ジンジツ】の節句)に食べると災いを除き、長寿福来を得られるという言い伝えで七草粥があるのは、ご存じだと思います。
今回は、夏の猛威が色濃く残っていますが、暦の上では9月と言えば『秋』!
現代の方には馴染みが薄いですが
『秋の七草』について紹介します。
『秋の七草』は春の七草と違い、摘んだり食べたりするものではなく観賞するものだそうです。
秋の野の花が咲き乱れる野原を「花野(はなの)」といい、花野を散策して短歌や俳句を詠むことが古来行われていました。
山上憶良(やまのうえ おくら)が詠んだ下記の2首の歌がその由来とされています。
・秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり)
かき数ふれば 七種(ななくさ)の花【万葉集】
・萩の花 尾花 葛花 なでしこの花 姫部志(をみなへし)
また藤袴(フジバカマ) ※朝貌(アサガオ)の花【万葉集】
※朝貌は桔梗にあたるようです。
秋の七草は
- 女郎花(オミナエシ)…女性にまつわる由来が多い花。「女飯」「女なるべし」の言葉の由来、また、花のやさしさを女性に見立ててつけた名前とも言われている。
花言葉は『美人』。
- 尾花【おばな】(ススキ)…キツネのしっぽに似ていることに由来すると言われている。 お月見にススキをそなえるのは 花穂が豊かに実り秋を意味しているから。
花言葉は『活力』。

- 桔梗(キキョウ)…万葉集では朝貌(アサガオ)と呼ばれていて星型の花を咲かせる ふくらんだつぼみが風船に似ていることから英名は『バルーンフラワー』。
花言葉は『愛情・誠実』など。

- 撫子(ナデシコ)…小さくて愛らしい花を子どもになぞらえた名前。この花にちなんで、奥ゆかしくたおやかな日本女性のことを大和撫子という。
花言葉は『純愛』。

- 藤袴(フジバカマ)…花や葉をもむといい香りがするため、昔は匂い袋に入れて身につけていた。
花言葉は『ためらい・躊躇』など。
- 葛(クズ)…野山のどこでもつるを伸ばす、繁殖力の強い植物。根は葛粉として食用に、つるは編んでカゴなどのつる細工に利用される。
花言葉は『芯の強さ』。
- 萩(ハギ)…万葉集の中で萩の花を詠んだ歌は141首あり圧倒的な数を誇る。新芽はお茶にして飲み、根は干して薬用に花は染料として用いられていた。
花言葉は『思案』。

覚え方の語呂がありました。『お・す・き・な・ふ・く・は』です。
秋の七草は観賞用の為、秋の七草粥はありませんが、野原など草木がある場所にひっそりと自生しているかもしれません。
近年、夏が長く感じ、秋を体感で感じることが短く、涼しさからだけではなく視覚で秋を感じるのも現代の人には良いのではないでしょうか。
夕方など、過ごしやすくてお時間のあるときに散歩などで観察してみて下さい。