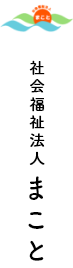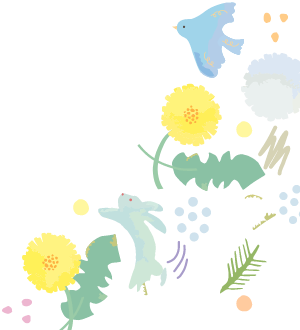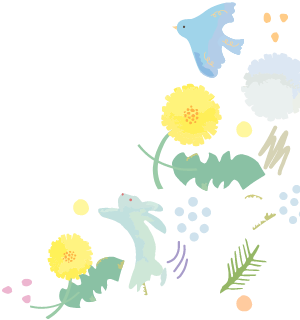こんにちは。
7月に入り、本格的な夏の訪れを感じる季節となりました。
今年は特に暑いですね。
夏の定番料理の一つに「そうめん」があります。
先日、しあわせの家で恒例行事の流しそうめんが開催されました。
大勢の方々が朝から楽しみにしていたようです。



食べきれないほどのそうめんをすくったり、
いつもよりたくさん召し上がられていました。
ところで皆様、そうめんの歴史はご存じですか?
日本のそうめんの歴史は、奈良時代に中国から伝来した「索餅(さくべい)」と呼ばれる唐菓子が起源とされています。
「索餅(さくべい)」とは小麦粉を水で練り、塩を加え縄状にして揚げるお菓子の事。
現代のチュロスのようなイメージです。
これは貴族たちが食べる高級食材でした。
そうめん作りは鎌倉時代から始まり、室町時代になると「索麺」や「素麺」の文字が使われるようになりました。このころからそうめんは寺院の間食として広がっていきました。
江戸時代になると生産が盛んになり、庶民の間でも食べられるようになりました。
古代から現代までの長い時を経て発展してきたそうめん。
歴史や由来に思いを馳せればいっそう美味しく感じる事ができるかもしれませんね。